 世界というのは、私が知らなかっただけで、ずいぶん剣呑であるのだなと思いました。いや、それでもさすがにこの世は清浄で、信頼と友愛を絆に、権利をお互いに尊重しあうばかりであるなんてことは思いもしていなかったんですが、けどそれでもここまでとはね……。権力、利益を拡大させるためには犯罪も辞さず、なにかことあらば暴力に訴える組織がおおっぴらに存在し、しかもそれを取り締まるべき国家が無力であるという事実。政治の腐敗は目に余るばかりで、裏取引があればまた傀儡といっていいくらいにまで癒着している政党がある。民衆はというと恐怖に屈し、本来は民衆の味方であるはずの警察、憲兵に協力しないばかりか逆に売る始末。これ、一体なんの話かといいますと、イタリアのマフィアでありまして、ピエルサンティの『イタリア・マフィア』によると、マフィアはイタリアのみならずヨーロッパからアメリカにまで手を広げ、その扱うものは武器、麻薬といった非合法の物品に始まり、果ては金融にいたるまで。マフィアというのは荒っぽく立ち回るだけのものだと思っていたんですが、いやいやとんでもない話。この本読んで、正直ぞっとしました。こんな恐ろしい組織が、それこそ普通に存在しているのかとあぜんとする思いでした。
世界というのは、私が知らなかっただけで、ずいぶん剣呑であるのだなと思いました。いや、それでもさすがにこの世は清浄で、信頼と友愛を絆に、権利をお互いに尊重しあうばかりであるなんてことは思いもしていなかったんですが、けどそれでもここまでとはね……。権力、利益を拡大させるためには犯罪も辞さず、なにかことあらば暴力に訴える組織がおおっぴらに存在し、しかもそれを取り締まるべき国家が無力であるという事実。政治の腐敗は目に余るばかりで、裏取引があればまた傀儡といっていいくらいにまで癒着している政党がある。民衆はというと恐怖に屈し、本来は民衆の味方であるはずの警察、憲兵に協力しないばかりか逆に売る始末。これ、一体なんの話かといいますと、イタリアのマフィアでありまして、ピエルサンティの『イタリア・マフィア』によると、マフィアはイタリアのみならずヨーロッパからアメリカにまで手を広げ、その扱うものは武器、麻薬といった非合法の物品に始まり、果ては金融にいたるまで。マフィアというのは荒っぽく立ち回るだけのものだと思っていたんですが、いやいやとんでもない話。この本読んで、正直ぞっとしました。こんな恐ろしい組織が、それこそ普通に存在しているのかとあぜんとする思いでした。
ずいぶん以前の話ですが、イタリアにいこうという直前のこと、海外によくいくという友人に聞いてみたのです。イタリアっていうのは危ないのかねって。そうしたら即座に危ないよって返事があって、けどその人はシチリアにいったりもしていた人で、シチリアに比べりゃそりゃましかもねともいってました。そう、シチリアといったらマフィアの本場で、石を投げたらマフィアに当たる(きっと命はないな)というほどにマフィアだらけといった人もいるけれど、けどこのマフィアっていうのは、互助組織みたいなものだからそんなに怖れるようなものでもないのだという人もいて、けど実際のところはどうなんだろうなあって思ってた。
ってのはですね、海外には人形を使って放送されるニュース番組というのがあるんだっていいますよね。これ、子供向けとかそういうんじゃないんです。なんで人形が使われるのかというと、出演者、関係者を特定させないための配慮であるというそうで、こうして身元を厳重に伏せたうえで報道されるのはマフィア関連のニュースなんだそうです。そう、身元がわかると報復されたりするんですよ。まあ端的にいうと殺されるんですが、私が以前テレビで見たそうした話では、報道関係者がやっぱり殺されていて、それも天下の往来で殺されていて、しかしそれでも報道は続けられる。これがジャーナリズムというものかと思って、肝を冷やしながらも、その覚悟には敬意のようなものを感じたものでした。
でも、こんなの過去の話だと思っていました。けど、どうもそうじゃないらしいんですね。『イタリア・マフィア』を読んでいると、その事例のほとんどは1960年代から1970年代くらいで、ずいぶん昔の話だなと思っていたんですが、いやいやそんなもんじゃなかった。確かにマフィアが死をふりまきながら暴れ回った時代こそはそうした昔の話でありますが、裁判は1980年代、1990年代にも逮捕、捜査は引き続いておこなわれており、そして何人もの捜査官が報復により殺されている。暗澹たる思いですよ。いや、ほんと、本読んでるだけで、この世には神も仏もないなあって気になれます。社会正義を胸にマフィアに立ち向かおうとする人たちが、現れては消えてゆく。銃殺、爆殺。対マフィア捜査官に任命されるということは、そう遠くないうちに殺されるのだということを宣告されたに同じという現実があり、けれどそれでも社会のため、公益のため、正義のためにと職務につくも、全うできずに消えてゆく。政治絡みの妨害、内通者、白昼堂々の犯罪でありながら目撃者も協力者も存在しないという、本当に砂を噛むような思いを追体験できる。それでも、本読んでるだけの私は命を危険にさらしているわけじゃありませんものね。と思うと、自分の命を投げ打つ覚悟でマフィアに立ち向かった人の崇高さというのは一体どういうものかと思うのです。
神も仏もない。バチカンがマフィアと癒着しているという状況の語られるにいたっては、そうした慣用句がもはや比喩にとどまっちゃいないよなあ。バチカン銀行を使って、麻薬密輸などの非合法活動によって得た巨大な資金を洗浄しているんだそうですね。でもって、バチカンと癒着しているばかりか、政治との癒着も甚だしくて、七度首相を務めたアンドレオッティがマフィアと癒着(というか、マフィアそのもの?)していたかと思えば、ついこないだまで首相をやってたベルルスコーニもマフィアとの関係を疑われるなど、この問題は長く、まさしく今の今まで続いているのだと感じさせて、だとしたら今私たちが見ているのはつかの間の平穏なのかとも思わせて、がっくりとする思いです。
以上は、思いつくままにに書いたもので、本に記されたことのごく一部、それこそ表面をなぞるだけに過ぎません。本書では、マフィアという組織について語られ、そしてマフィアとの戦いについてが語られ、そしてさまざまな組織機関との癒着が語られ、それらは時に前後して語られるために時系列がわかりにくくなることもありますが、けれどそれほど難しく、ややこしく書かれているわけではありません。現状、これを読んでみて私の中に問題めいたものがあるとすれば、こうした一連のことをこの一冊で判断してよいものかという疑念でありまして、それはつまりこの本に書かれていることがにわかには信じがたいといっています。本当にこんなに強烈なのか。本当に、これほどの組織が大手を振って、我が物顔に活動しているのか。どこまでを真実として諒解すればいいのか、あるいはすべて? そうしたことを判断するには、あまりに私の知識は少なすぎます。
そして、またこういう感想を持ったことも書いておかねばならないと思います。果たして、これらイタリア・マフィアについて、他人事のように感じていられるものなのかということです。
先日、長崎市長が銃撃されるという事件があったことはきっとご存じでしょう。あの事件は、その動機としては個人的怨恨(それも逆恨みめいたもの)であるように報道されていますが、しかし怨恨を抱くにいたるまでのあいだに、対行政暴力が存在したともいわれています。そしてこうした暴力は、長崎に限らずこの国のいたるところで起きているというようにも報道されていて、そうした国に暮らし、そうした暴力に無関心でいた日本人は、果たしてイタリア人のことを他人事のように批判、非難することはできるのだろうかということです。
イタリア・マフィアは映画『ゴッドファーザー』でもって一躍アンチヒーローないしはダーティヒーローめいたオーラを纏うにいたりましたが、それは日本の暴力組織においても似たようなもので、どこかにアウトローとしての格好良さというのが付随しているように思います。ですが、現実はというと決してそんなきれい事で語れるものではないというのは周知のことで、ですがそうした事実を前にして戦うことはできるのか、真っ向から立ち向かうことができるかといわれると、足のすくむ思いもします。
だから、おそらくは、『イタリア・マフィア』に書かれていることというのは、私たち日本人にとっては遠い世界のように感じられるものの、違った側面においてまったく同じ状況にあるということなのではないかと思います。ここに書かれたことを他人事のように感じていてはいけないのではないかと感じます。
- ピエルサンティ,シルヴィオ『イタリア・マフィア』朝田今日子訳 (ちくま新書) 東京:筑摩書房.2007年。
 ロストロポーヴィチが亡くなりました。享年八十歳。まあ、お歳だもんなあとは思ったのですが、けれどショックはショック。私が昔聴いて親しんでいた名前がこうして一人一人鬼籍に入っていくというのは、ただただ寂しく悲しいことであろうかと思います。これが世の理りとはわかっていながらも、やっぱりね。悲しさとか痛ましさというようなものは、そこにたとえどういう理由や理屈があったとしても、消えるものではないと思いますから。ロストロポーヴィチといえば、私、ずっと欲しかったものがありまして、それはLDであったのですが、J. S. バッハの『無伴奏チェロ組曲』を収録したもの。演奏があり解説がありという、その解説に興味があったのです。けど、私はこのLDは結局買うにいたらず、DVDになってくれたらなあと思っていた頃にはDVD化せず、私がDVDから離れている間にDVD化して、今はもう入手困難になっているという、一体なんなんでしょうねこの縁のなさは。
ロストロポーヴィチが亡くなりました。享年八十歳。まあ、お歳だもんなあとは思ったのですが、けれどショックはショック。私が昔聴いて親しんでいた名前がこうして一人一人鬼籍に入っていくというのは、ただただ寂しく悲しいことであろうかと思います。これが世の理りとはわかっていながらも、やっぱりね。悲しさとか痛ましさというようなものは、そこにたとえどういう理由や理屈があったとしても、消えるものではないと思いますから。ロストロポーヴィチといえば、私、ずっと欲しかったものがありまして、それはLDであったのですが、J. S. バッハの『無伴奏チェロ組曲』を収録したもの。演奏があり解説がありという、その解説に興味があったのです。けど、私はこのLDは結局買うにいたらず、DVDになってくれたらなあと思っていた頃にはDVD化せず、私がDVDから離れている間にDVD化して、今はもう入手困難になっているという、一体なんなんでしょうねこの縁のなさは。 四コマ漫画はただ面白おかしいというだけのジャンルではなくなった、というのは今では周知のことになっていようかと思うのですが、こと岬下部せすなの『ことゆいジャグリング』においては、そうした傾向というのを強く感じます。一見すれば、人付き合いの苦手な娘高城唯が、まったく対照的とも思える明るく人懐こいサーカスの娘山吹小鳥に振り回される、その様を面白がる漫画であるのですが、実はそれだけではないというのですからたいしたものと思います。というのも私は、この漫画のラスト、クライマックスを待つ数回においてそうしたテーマを語られるまで、ちっともそうしたところに気付くことなく、ただ人付き合い苦手な娘たちがとかく元気な小鳥に引きずられて、少しずつ心を開いていく、それだけの漫画だと思っていたのですよ。そう、私はこの漫画を読んで、ほんの一面にしか心を向けていなかった。ああ、反省だわ。いや、ほんとにそんな気分です。
四コマ漫画はただ面白おかしいというだけのジャンルではなくなった、というのは今では周知のことになっていようかと思うのですが、こと岬下部せすなの『ことゆいジャグリング』においては、そうした傾向というのを強く感じます。一見すれば、人付き合いの苦手な娘高城唯が、まったく対照的とも思える明るく人懐こいサーカスの娘山吹小鳥に振り回される、その様を面白がる漫画であるのですが、実はそれだけではないというのですからたいしたものと思います。というのも私は、この漫画のラスト、クライマックスを待つ数回においてそうしたテーマを語られるまで、ちっともそうしたところに気付くことなく、ただ人付き合い苦手な娘たちがとかく元気な小鳥に引きずられて、少しずつ心を開いていく、それだけの漫画だと思っていたのですよ。そう、私はこの漫画を読んで、ほんの一面にしか心を向けていなかった。ああ、反省だわ。いや、ほんとにそんな気分です。 『まんがタイムきらら』を筆頭に『キャラット』、『MAX』と拡大してきた、マニア層を対象とした四コマ誌ですが、私はこれらを読んで、時々よくわからなくなることがあります。いったいなにがわからないのかというと、その対象とする読者層でして、多分若い人が読むんだろうと思うんですけど、高校生とか大学生とか? いや、けどそれはどうだろう。一説には女子中学生あたりが読んでいるなんて話もあるんだけど、にわかには信じられません。だって、これ読んでいる人を具体的に見たことがないんですよ、私。それに、この雑誌に現れる小ネタやなんかは微妙に二十代後半から三十代くらいを狙っている。まあこれはそれくらいの世代の作家が多いということだと思うんですが、けどそれにしても多すぎやしないか? メインターゲットが十代から二十代前半だとしたらですよ、ああいう小ネタ群、ほとんどわからんだろう。と、そんな風に思っているから私には、この『イチロー!』が妙に新鮮に感じられて、主人公は高校を卒業したところの女の子。ああ、多分雑誌が狙っている年齢層というのはこのくらいなんだろうなと感じられて、なんかほっとしたのでした。
『まんがタイムきらら』を筆頭に『キャラット』、『MAX』と拡大してきた、マニア層を対象とした四コマ誌ですが、私はこれらを読んで、時々よくわからなくなることがあります。いったいなにがわからないのかというと、その対象とする読者層でして、多分若い人が読むんだろうと思うんですけど、高校生とか大学生とか? いや、けどそれはどうだろう。一説には女子中学生あたりが読んでいるなんて話もあるんだけど、にわかには信じられません。だって、これ読んでいる人を具体的に見たことがないんですよ、私。それに、この雑誌に現れる小ネタやなんかは微妙に二十代後半から三十代くらいを狙っている。まあこれはそれくらいの世代の作家が多いということだと思うんですが、けどそれにしても多すぎやしないか? メインターゲットが十代から二十代前半だとしたらですよ、ああいう小ネタ群、ほとんどわからんだろう。と、そんな風に思っているから私には、この『イチロー!』が妙に新鮮に感じられて、主人公は高校を卒業したところの女の子。ああ、多分雑誌が狙っている年齢層というのはこのくらいなんだろうなと感じられて、なんかほっとしたのでした。
 なんでか私は金髪好きという誤解をされているのですが、けど、ほんとになんでなんでしょうかね。金髪大好きだなんて、ここでもどこでもあそこでも一度もいったことないのに、もしかして金髪好き? といわれて、いやあえらい誤解だ。あんときゃたまたま、
なんでか私は金髪好きという誤解をされているのですが、けど、ほんとになんでなんでしょうかね。金髪大好きだなんて、ここでもどこでもあそこでも一度もいったことないのに、もしかして金髪好き? といわれて、いやあえらい誤解だ。あんときゃたまたま、



 ギターのための『セクエンツァ』があると知って、矢も盾もたまらずに注文したルチアーノ・ベリオ『
ギターのための『セクエンツァ』があると知って、矢も盾もたまらずに注文したルチアーノ・ベリオ『
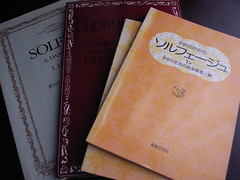
 先日、『ひだまりスケッチブック』を買いにいこうと思ったと
先日、『ひだまりスケッチブック』を買いにいこうと思ったと

 九州男児『
九州男児『 頼んでいた
頼んでいた
