武重そして次作。『カルドセプト』は現在、新プロジェクトを進めております。
鈴木開発は僕ら大宮ソフトが、担当しています。
武重ハードはニンテンドーDS。パブリッシャーは、セガさんです。
ほら、私、先月にいってたじゃないですか。心機一転、Nintendo DSあたりで出してくれないかなあ
ってやつですよ。それが思わずかなってしまったわけであります。わー、嬉しいなあ。出るのは来年のいつからしいですが、ほんとその日が待ち遠しいと思います。いやあ、ほんと、嬉しいニュースでありました。
私が、Nintendo DSで出して欲しいといっていた、その理由というのをちょっと引用してみましょう。
ハード持ち寄って通信対戦するのも簡単だし、WiFi使ったオンライン対戦も可能だし。なにより、どこででも遊べるというのは嬉しい。キャラクターやマップをポリゴンで表現する必要なんてないんだし、それこそオリジナルカルドセプト風にドット絵でオッケー。むしろ、私はその方が嬉しい。だから、DSで出て欲しいなあ。カルドセプトの他人の手札が見える仕様はそのままで、けどオプションで手札を伏せられるようになっても面白いんではなくて?
Nintendo DSは外部メディアにデータを書き出せない(オフィシャルではそうよね?)から、ソフトとセプターデータが不可分となり、ちょっとこのへんはやだなあと思わないでもないですが、まあセカンド・エキスパンションでもデータコピー不可の呪いがあったわけですから、仕方がないと思いましょう。それよりもメリットですよ。ハードを持ち寄って対戦可能であることはもちろんのこと、WiFi対戦もできるようになるに違いないと思ってるんですが、そうなると私にとっては初のネットワーク対戦可能カルドになるわけです。WiFiだから場所も選びませんでしょう? それこそ居間で、自室で、さすがに相手のいることですからいつでもというわけにはいかないでしょうが、好きな場所で気軽に対人戦できるというのは魅力であります。だってね、カルドセプトは対人戦をしてなんぼのゲームですよ。残念ながらCPUではぬるすぎるのです。対人戦、負けそうになったら切断するやつがいるよ、なんていいますが、そのへんは自動でハウント状態に移行するとかは無理なのかな。セプターが復帰したらハウントが解けるって感じで。とにかくオンラインが一人でもいる限り続くような仕様になってるとベストだろうとは思うんだけど、そんなにうまくいくもんかどうかはわかりません。
携帯機でカルドセプト、となると、モノポリースタイル — 本腰入れて戦う従来の路線に、携帯電話で展開されたカードバトルスタイル — アナザー・チャプター、もあってもいいのかなと思います。あと、カルドセプトはカードをコンプリートしてからがスタート地点という、導入において多少敷居の高さのあるゲームですから、一見さんでも楽しめるようなゲストモードが欲しいです。ダウンロードプレイ限定でいいんです。数種類の構築済みブックから選べたり、ランダムで押し付けられたり(開いてみるまでわからない!)、初心者相手にする上級者なら全カードランダムでいいんじゃない? ちょうどいいハンデだよ。ろくな武器はいってない! とか、ここぞというときになぜゴブリン! とか、わあわあいいながら遊ぶのも目先が変わって楽しいかも知れないし、もしかしたら苦し紛れの新コンボ発見なんてのもあるかも知れない。とにかく、はじめてカルドセプトに触れる人に、このゲーム面白い! って思ってもらえるようなモードが欲しいんです。そうして目覚めた人の中から、明日のセプターが生まれるとなれば、どんなにか素敵だろうと思います。
いずれにしても、楽しいものであれば幸いです。キャラクターとかはポリゴンじゃなくていいんで、というのも無印カルドの魔女っ子が好きな私です、中途半端なポリゴンはいらん、2D、ドット絵最高! 見栄えは確かに大事だし、カードのシリアスイラストがなくなったりしたらいやではあるんですが、それよりも重要なのはゲーム性です。とにかくこれ面白いからやってみ、と人に勧めてまわりたくなるような出来であれば最高です。
蛇足
サターンではヘッジホッグ、PSではバンディクート、じゃあDSでは配管工が出たりするのかな? かな? こうした、にやりとできるような遊びがあるのかどうか、ちょっと楽しみであったりします。
Xbox 360
PlayStation2
Dreamcast
PlayStation
SEGA SATURN
コミックス
- かねこしんや『Culdcept』第1巻 (マガジンZKC) 東京:講談社,2000年。
- かねこしんや『Culdcept』第2巻 (マガジンZKC) 東京:講談社,2001年。
- かねこしんや『Culdcept』第3巻 (マガジンZKC) 東京:講談社,2002年。
- かねこしんや『Culdcept』第4巻 (マガジンZKC) 東京:講談社,2004年。
- かねこしんや『Culdcept』第5巻 (マガジンZKC) 東京:講談社,2005年。
- かねこしんや『Culdcept』第6巻 (マガジンZKC) 東京:講談社,2007年。
- 以下続刊
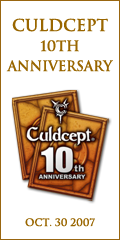
 トラブルに対処すべく出動していた私、なんとかやっつけてやれやれ事務所に戻ったら、係長が呼ぶんです。ま、またトラブルか!? 正直もう勘弁して欲しいと恐る恐る寄っていったらば、トラブルどころじゃないですよ。なんと、GR DIGITALの後継機が発表されたそうじゃありませんか。わお、そろそろ出るらしいとは聞いていたけど、ついに出たか。見れば、広角単焦点という基本コンセプトはそのままに、画素数を上げ、低ノイズ高画質を目指したという、まさしく正常進化というにふさわしいものであります。この目立った機能アップを目指さないっていうスタンスは、GRのコンセプトが秀逸であること、またそのコンセプトが受け入れられているということを明らかにしていると思います。そして、カメラとしての完成度の高さを雄弁に物語るものであると思います。
トラブルに対処すべく出動していた私、なんとかやっつけてやれやれ事務所に戻ったら、係長が呼ぶんです。ま、またトラブルか!? 正直もう勘弁して欲しいと恐る恐る寄っていったらば、トラブルどころじゃないですよ。なんと、GR DIGITALの後継機が発表されたそうじゃありませんか。わお、そろそろ出るらしいとは聞いていたけど、ついに出たか。見れば、広角単焦点という基本コンセプトはそのままに、画素数を上げ、低ノイズ高画質を目指したという、まさしく正常進化というにふさわしいものであります。この目立った機能アップを目指さないっていうスタンスは、GRのコンセプトが秀逸であること、またそのコンセプトが受け入れられているということを明らかにしていると思います。そして、カメラとしての完成度の高さを雄弁に物語るものであると思います。 実は、四コマ漫画であれこれ書くのは非常に難しいのです。これはとりわけきらら系列に顕著で、理由は簡単、気を抜くとどの漫画に対しても同じようなことを書いてしまうから。あるいは、面白いと思っていながらも、その面白さを言語化しにくいということもあるからかと思います。このへん、明確な物語の流れを持った漫画については書きやすく、だってその漫画の持つ面白さの独自性云々をそれほど考えないでもいいですからね。物語を追うことで私の感じたことを書けばいい。しかもありがたいことに、作者の側で物語が独自のものになるよう工夫されてますから、なおさら楽というわけです。と、なんでいきなりこんな愚痴じみたことを書くのかというと、先達て買いました『あっちこっち』という漫画、面白いのだけど、それを思ったままにただ書いても、多分この漫画の独特の味というのは伝わらんと思ったからなのです。
実は、四コマ漫画であれこれ書くのは非常に難しいのです。これはとりわけきらら系列に顕著で、理由は簡単、気を抜くとどの漫画に対しても同じようなことを書いてしまうから。あるいは、面白いと思っていながらも、その面白さを言語化しにくいということもあるからかと思います。このへん、明確な物語の流れを持った漫画については書きやすく、だってその漫画の持つ面白さの独自性云々をそれほど考えないでもいいですからね。物語を追うことで私の感じたことを書けばいい。しかもありがたいことに、作者の側で物語が独自のものになるよう工夫されてますから、なおさら楽というわけです。と、なんでいきなりこんな愚痴じみたことを書くのかというと、先達て買いました『あっちこっち』という漫画、面白いのだけど、それを思ったままにただ書いても、多分この漫画の独特の味というのは伝わらんと思ったからなのです。 表紙を見たときの感想は忘れもしません。うわっ、彩度低っ。白地バックの画面両端に配置されたタイトルは、あくまでデザイン優先、可読性は押さえられ、背景に引っ込んでしまっています。表紙で一番目立つ位置、すなわち画面中央を陣取るアリスにしても、これでもかの黒仕様。めっちゃくちゃ彩度の低い、極限まで色味の押さえられた衣装は、それこそ濃淡の美の世界。そして、これが白背景に映えるのですよ。って、当たり前ですが。なんてったって極端なハイコントラストですもの。むしろ攻撃的といっていいくらいの印象をふりまいて、そしてそれはアリスも同様です。傘のうちから肩越しに見返るその雰囲気も婉然として、金髪ツインテール、大きな黒リボン、クマも濃いつり目に覗く虹彩は赤! そう、赤がこの彩度の低い表紙において非常に効果的であるのです。タイトル一文字目の赤は背景に追いやられたタイトルに注意を向かわせ、アリスの目は射すくめるかのような熱を帯びてこちらに向かってきます。いや、それにしてもいい表紙だわ。私が無類のハイコントラスト好きであることをさっ引いたとしても、売り場にて目を引くことにかけてはなかなかのものでありました。ただこのインパクトの強さが、四コマ漫画を好む読者にどう働き掛けるかなんですが、 — いい方向に向かわしてくれたら嬉しいなあって思うんですが、このへん実際どうでしょう。
表紙を見たときの感想は忘れもしません。うわっ、彩度低っ。白地バックの画面両端に配置されたタイトルは、あくまでデザイン優先、可読性は押さえられ、背景に引っ込んでしまっています。表紙で一番目立つ位置、すなわち画面中央を陣取るアリスにしても、これでもかの黒仕様。めっちゃくちゃ彩度の低い、極限まで色味の押さえられた衣装は、それこそ濃淡の美の世界。そして、これが白背景に映えるのですよ。って、当たり前ですが。なんてったって極端なハイコントラストですもの。むしろ攻撃的といっていいくらいの印象をふりまいて、そしてそれはアリスも同様です。傘のうちから肩越しに見返るその雰囲気も婉然として、金髪ツインテール、大きな黒リボン、クマも濃いつり目に覗く虹彩は赤! そう、赤がこの彩度の低い表紙において非常に効果的であるのです。タイトル一文字目の赤は背景に追いやられたタイトルに注意を向かわせ、アリスの目は射すくめるかのような熱を帯びてこちらに向かってきます。いや、それにしてもいい表紙だわ。私が無類のハイコントラスト好きであることをさっ引いたとしても、売り場にて目を引くことにかけてはなかなかのものでありました。ただこのインパクトの強さが、四コマ漫画を好む読者にどう働き掛けるかなんですが、 — いい方向に向かわしてくれたら嬉しいなあって思うんですが、このへん実際どうでしょう。
 ああもう、可愛い、可愛い、面白いってことで、もうどうしようもないんですが、なにが可愛いのかといいますと、『
ああもう、可愛い、可愛い、面白いってことで、もうどうしようもないんですが、なにが可愛いのかといいますと、『 ずいぶん前に、
ずいぶん前に、

 表紙買いをきっかけにしてはまってしまった漫画家というと、篠房六郎が今のところ筆頭かなあなんて思うんです。これまで何度も何度も書いてきた『
表紙買いをきっかけにしてはまってしまった漫画家というと、篠房六郎が今のところ筆頭かなあなんて思うんです。これまで何度も何度も書いてきた『
 このところ、表紙にひかれて買った漫画を連続して取り上げていますが、この表紙買いっていうの、改めて考えると、結構成立する条件が厳しいんです。まず、表紙買いっていうくらいだから、内容に関する知識が事前にあっちゃ駄目なわけで、それに、この作者わりと好きだったんだ、っていうのもちょっと違う。まったく知らないとか、ちょっと知ってるだけとか、それくらいの乏しい知識の中、表紙に引きつけられるままに買ってしまう。やっぱりこうでないといけません。だから表紙買いされる漫画ってのは自然マイナー作に偏りを見せて、だってメジャー作だとどうしても評判とか耳に入ってしまいますから。レビューを読んだ、友達が面白いっていってた、なんだか賞とったらしいよ、などなど、こうなっちゃ表紙買いっていえませんよね。と、こんな具合に条件をどんどん厳しくしていくと、純粋に表紙買いといえるものってほとんどないように思います。ですが、そんな乏しい表紙買い体験の中、これぞといえるものが私にはあるのです。それは、西川魯介の『屈折リーベ』です。
このところ、表紙にひかれて買った漫画を連続して取り上げていますが、この表紙買いっていうの、改めて考えると、結構成立する条件が厳しいんです。まず、表紙買いっていうくらいだから、内容に関する知識が事前にあっちゃ駄目なわけで、それに、この作者わりと好きだったんだ、っていうのもちょっと違う。まったく知らないとか、ちょっと知ってるだけとか、それくらいの乏しい知識の中、表紙に引きつけられるままに買ってしまう。やっぱりこうでないといけません。だから表紙買いされる漫画ってのは自然マイナー作に偏りを見せて、だってメジャー作だとどうしても評判とか耳に入ってしまいますから。レビューを読んだ、友達が面白いっていってた、なんだか賞とったらしいよ、などなど、こうなっちゃ表紙買いっていえませんよね。と、こんな具合に条件をどんどん厳しくしていくと、純粋に表紙買いといえるものってほとんどないように思います。ですが、そんな乏しい表紙買い体験の中、これぞといえるものが私にはあるのです。それは、西川魯介の『屈折リーベ』です。
 表紙で買ったシリーズはやらないみたいなことをいってましたが、なんでかそっち方面のスイッチが入ってしまったようで、そう、本日取り上げるのも、表紙買いタイトルです。三浦靖冬の『おつきさまのかえりみち』。残念ながらAmazonに画像が用意されてなかったので、実際にどんな表紙であったかお伝えすることはできませんが、ちょっとサイバーパンク風、 — いや違うなあ。不透明水彩で色付けされたっぽい少し濁って重めの表紙は、レトロさと温かみにあふれていて、実際の話、すごく素敵なイラストレーションに仕上がっています。遠景にはどこか懐かしさを感じさせる町並みが広がり、近くには昭和中期を彷彿とさせるディテールに彩られたガジェットが。金魚が宙を泳ぎ、生身もあればブリキのおもちゃ思わせる外観のものもあって、そしてその中央には青いミニのワンピース(スクール水着モチーフ)を着た少女が一人、行き過ぎようとする金魚に手を伸ばそうとしている、そういう表紙であったのです。
表紙で買ったシリーズはやらないみたいなことをいってましたが、なんでかそっち方面のスイッチが入ってしまったようで、そう、本日取り上げるのも、表紙買いタイトルです。三浦靖冬の『おつきさまのかえりみち』。残念ながらAmazonに画像が用意されてなかったので、実際にどんな表紙であったかお伝えすることはできませんが、ちょっとサイバーパンク風、 — いや違うなあ。不透明水彩で色付けされたっぽい少し濁って重めの表紙は、レトロさと温かみにあふれていて、実際の話、すごく素敵なイラストレーションに仕上がっています。遠景にはどこか懐かしさを感じさせる町並みが広がり、近くには昭和中期を彷彿とさせるディテールに彩られたガジェットが。金魚が宙を泳ぎ、生身もあればブリキのおもちゃ思わせる外観のものもあって、そしてその中央には青いミニのワンピース(スクール水着モチーフ)を着た少女が一人、行き過ぎようとする金魚に手を伸ばそうとしている、そういう表紙であったのです。 ずっと昔のことなのですが、
ずっと昔のことなのですが、
 実に私という人間は趣を解さない男でありまして、巷にいうブルマやスクール水着、それらの価値であるとか魅力であるとか、まったくもってわからないのです。ほんと、あれらのどこがいいのだろう、おおっぴらに口にはしないものの、ずっとそんな風に思ってきたのです。けれど、今月の『
実に私という人間は趣を解さない男でありまして、巷にいうブルマやスクール水着、それらの価値であるとか魅力であるとか、まったくもってわからないのです。ほんと、あれらのどこがいいのだろう、おおっぴらに口にはしないものの、ずっとそんな風に思ってきたのです。けれど、今月の『 Mac OS Xの新バージョン、
Mac OS Xの新バージョン、
 こないだ職場の人と雑談してまして、
こないだ職場の人と雑談してまして、
